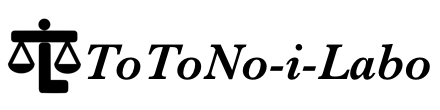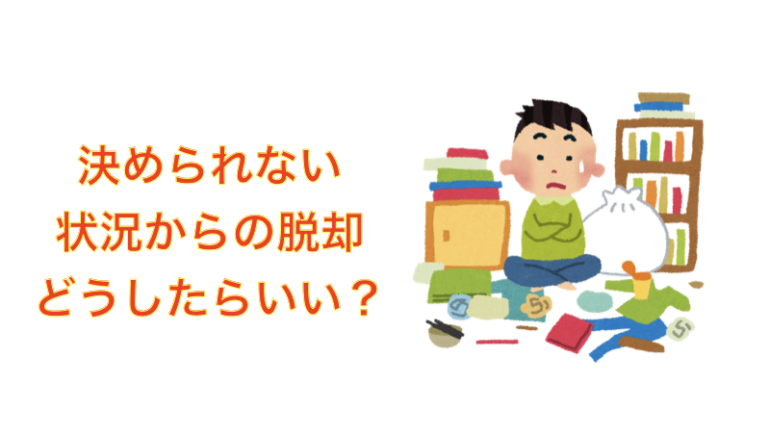「これ、もう要らないし捨てようかな。でもまだ使えるしなあ。どうしようか。。。」
整理を行っていると、こういった「決められない」「先延ばしにしたい」心情にも出くわします。
そして、「また今度にしよう」といって棚や箱に”隠し”、その存在すら忘れ去られてしまう。
何がこのようなことを引き起こすのでしょうか?
この記事では「決定回避の法則」という視点から考えてみます。
Contents
決定回避の法則とは
人は選択肢が多すぎると、選ぶ事自体を先延ばしにしたり避ける傾向がある。間違えて損したくないから。
人は新しい選択肢よりも、慣れた選択肢を選びがち。選択を間違って損するくらいなら何も選ばない(現状維持の法則とも)。
これは、選択肢が多すぎる他、決断に伴う責任やリスクを感じたりするときに特に顕著になります。
決定回避が起こるメカニズム
なぜ、人は選択肢が多いと決められなくなってしまうのでしょうか? それは次の心理メカニズムから説明できます。
https://studyhacker.net/ketteikaihi
- 選択疲れ
- 選択肢を吟味する際、脳は大量のエネルギーを消費。選択肢が多いほど疲労が蓄積し、判断力が低下します。
- 損失回避
- 人は損失を避けることを優先する傾向があります。「ほかの選択肢の方がよかったかも」という後悔を恐れ、決定を先送りにしてしまいます。
- 情報過多
- 選択肢が増えるほど比較検討すべき情報も増加。情報処理の負担が限界を超え、思考が停止してしまいます。
- 完璧主義
- 選択肢が多いほど「最善の選択」へのプレッシャーも増大。完璧を求めすぎることで、かえって決断が難しくなります。
整理中に起こる決定回避の例
選択疲れ
(2時間後、、、)
まだ終わらない、、、はぁ~、疲れてもう決められないよ~。
や~めたっ!
損失回避
情報過多
も~どうしたいいかわからない!
完璧主義
デメリットが顕現したときは、どう対処すべきかな、、、
他に漏れている検討事項はないかな??
こういった要因が複雑に絡み合い、「決められない」状態を引き起こしていると考えられます。
負荷を減らし、効率的に進める方法
”選択”を企画する
「選択疲れ」を軽減するために、ただやみくもに整理を始めるのではなく、事前に計画しておきましょう。例えば、
- エリア限定
- 一度に部屋全体を片づけようとせず、例えば「デスクの引き出しだけ」「クローゼットの左側だけ」と小さく区切る。
- 時間限定
- 一気に片づけようとせず、例えば「毎日30分だけ」「1日3時間以上はしない」と時間を区切る。
- カテゴリ限定
- 目についたものを片っ端から片づけようとせず、例えば「靴だけ」「文房具だけ」とカテゴリで区切る。
などが挙げられます。
小さな成功を積み重ねる
「損失回避」「完璧主義」を軽減・克服するためには、達成感・成功体験を得ることが大事です。
最初に簡単なもの(例: 古いレシートや壊れたペン)から片づけ始めると、「できた!」という自信がつき、次のステップに進みやすくなります。
「できた!」を積み重ねて決断力を鍛えましょう。
情報収集はほどほどに
「情報過多」にならないよう、情報は厳選しましょう。収集に時間制限を設けて、その時間内で最善を尽くしましょう。
また、どんな情報よりも、自分の体験や感じたことを優先することで、決断のブレを少なくすることができます。
即断即決を脇におく
「成功を収めるためには、迅速な意思決定が不可欠」とはビジネスではよく聞くフレーズですが、片づけにおいてはそうとも限りません。
片づけ(特に整理)においては、「何を捨てるか」「何を残すか」を決めるのが、あなたにとっては重大な決断になることが多いので、時間に囚われず、中途半端にせず、納得するまでやりきることがむしろ大事だったりします。
やりきる体験を重ねることで、あなたにとっての「いい塩梅の選択」が見つかっていくでしょう。
意図的な選択回避
選択回避の負担を軽減するために、「意図的に」先送りします。
選択回避の負担は、「後悔するかも」といった恐れや不安から生まれます。これらを減らすために、例えば、
- 「保留ボックス」で第3の選択肢を作る
- 捨てるか迷うものは一旦「保留」にして、見直す時期を決める。期限が来たら再度整理する。これにより、即決の負担を軽減する。
- 写真を撮る
- 捨てる前に思い出の品を写真に残し、「物を失う感覚」を軽減させる。
などが挙げられます。
さいごに
決定回避の法則は、選択肢が多すぎると何も選ばなくなってしまう心理メカニズム。選択を間違えたくない、損失回避の心理が働きます。
「決定回避」は誰もが経験する自然な心理現象です。この傾向を理解し、適切な対処法を知ることで、よりすばやい決断ができるようになります。
紹介した「負荷を減らし、効率的に進める方法」を活用すれば、納得した整理へとつながるはずです。
まずはできるところから始めてみましょう。